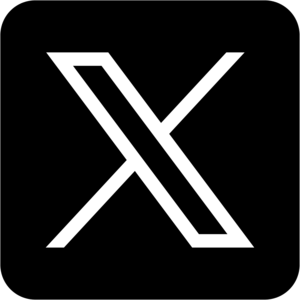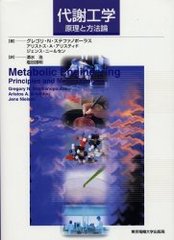대체공학
代謝工学목차
內容
「代謝工学」とは、分子生物学の急速な発展の上に、 特定の物質の生産を主要な目標として生まれてきた新しい科学である。 将来、 例えば夢の新薬開発や環境修復への応用など、 無限の可能性を秘めている。
人間が古くから利用してきた生物の代謝反応として、 醸造や発酵などがある。 近年は遺伝子工学やバイオテクノロジーの応用により、 ある程度これを制御できるようになった。 しかし、 それはまだ多くの偶然性や経験的要素に依存した、 「合成」に特長のある科学である。
これに対して代謝工学は、 「合成」だけでなく、 生物が高度に組織化した代謝ネットワークを「解析」して応用することに力点をおいた科学である。
本書はその基本原理から具体的方法論までを、 代謝経路の改変、 代謝の流れの定量的取り扱いなどを軸に解説し、 工学的応用に向けた、 まったく新しい生物化学工学のテキストとなった。
目次
日本語版への序文
序 文
訳者序文
1. 代謝工学のエッセンス
1. 1 代謝工学の重要性
1. 2 本書の概要
2. 細胞の代謝
2. 1 細胞の代謝の概観
2. 2 輸送反応
2. 2. 1 受動輸送
2. 2. 2 促進拡散
2. 2. 3 能動輸送
2. 3 エネルギー代謝
2. 3. 1 解糖系
2. 3. 2 発酵経路
2. 3. 3 TCAサイクルと酸化的リン酸化反応
2. 3. 4 アナプレロティック反応(補充反応)
2. 3. 5 脂肪,脂肪酸,アミノ酸の異化代謝
2. 4 生合成反応
2. 4. 1 アミノ酸の生合成
2. 4. 2 核酸,脂肪酸,その他の構成要素の生合成
2. 5 高分子化反応
2. 6 細胞増殖におけるエネルギー論
3. 細胞内反応のモデル
3. 1 細胞内反応の化学量論
3. 2 反応速度
3. 3 ダイナミックマスバランス
3. 4 収率係数と線形関係式
4. 物質収支とデータコンシステンシー
4. 1 ブラックボックスモデル
4. 2 元素バランス
4. 3 熱収支
4. 4 冗長な情報を用いたシステムの解析 ― 大きな測定誤差の同定
5. 代謝経路の調節
5. 1 酵素活性の調節
5. 1. 1 酵素カイネティクスの概要
5. 1. 2 単純な可逆阻害システム
5. 1. 3 不可逆阻害
5. 1. 4 アロステリック酵素:協調的調整
5. 2 酵素濃度の調節
5. 2. 1 転写開始の制御
5. 2. 2 翻訳の制御
5. 3 グローバルなコントロール:細胞全体のレベルでの調節
5. 4 代謝ネットワークの調節
5. 4. 1 分岐点の分類
5. 4. 2 共役した反応とグローバルな通貨代謝物質
(カレンシーメタボライト)
6. 代謝経路の改変の実例 ― 代謝工学の実際
6. 1 生産物収率と生産性の向上
6. 1. 1 エタノール
6. 1. 2 アミノ酸
6. 1. 3 有機溶剤
6. 2 微生物が利用可能な基質の範囲の拡張
6. 2. 1 ペントースの代謝を利用したエタノール生産の代謝工学
6. 2. 2 セルロース,ヘミセルロース分解
6. 2. 3 ラクトースとホエーの利用
6. 2. 4 シュクロースの利用
6. 2. 5 デンプン分解微生物
6. 3 新規生産物質の開発
6. 3. 1 抗生物質
6. 3. 2 ポリケタイド
6. 3. 3 ビタミン
6. 3. 4 バイオポリマー
6. 3. 5 バイオ色素
6. 3. 6 水 素
6. 3. 7 ペントース:キシリトール
6. 4 細胞特性の改良
6. 4. 1 窒素代謝の変更
6. 4. 2 酸素消費の強化
6. 4. 3 オーバーフロー代謝の抑制
6. 4. 4 基質消費経路の変更
6. 4. 5 遺伝子の安定性の維持
6. 5 生体異物(外来性化学物質)の分解
6. 5. 1 ポリ塩化ビフェニール(PCB)
6. 5. 2 ベンゼン,トルエン,p-キシレン混合物(BTX)
7. 代謝経路の合成
7. 1 代謝経路合成のアルゴリズム
7. 2 アルゴリズムの全体像
7. 3 ケーススタディ:リジン生合成
7. 3. 1 オキザロ酢酸の役割
7. 3. 2 その他の可能性のある経路
7. 3. 3 最大収率を与える反応
7. 4 アルゴリズムに関するディスカッション
8. 代謝フラックス解析
8. 1 理 論
8. 2 冗長な状態(over-determined)のシステム
8. 3 under-determined
(システムを一意に決定できない状態)なシステム― 線形計画法
8. 4 感度解析
9. 同位体標識による代謝フラックスの実験的な決定法
9. 1 同位体標識の濃縮度分率からの直接的なフラックスの決定
9. 1. 1 遷移状態の強度測定によるフラックスの決定
9. 1. 2 代謝物質と同位体化合物の定常状態の実験
9. 2 代謝化合物の同位体を完全列挙する方法とその応用
9. 2. 1 標識されたピルビン酸から生成する
TCAサイクル中の同位体代謝化合物の分布
9. 2. 2 標識された酢酸を用いた
TCAサイクル中の代謝物質同位体の分布
9. 2. 3 実験データの解釈
9. 3 代謝物質の炭素バランス
9. 3. 1 直接的な代謝物質の炭素バランス
9. 3. 2 原子マッピング行列の利用
10. 代謝フラックス解析の応用
10. 1 コリネ細菌によるアミノ酸生産
10. 1. 1 グルタミン酸生産菌の生化学と調節機構
10. 1. 2 理論収率の計算
10. 1. 3 C. glutamicumにおけるリジン生産の代謝フラックス解析
10. 1. 4 C. glutamicumにおける特定の酵素を欠失させた変異株の
代謝フラックス解析
10. 2 動物細胞培養における代謝フラックス
10. 2. 1 細胞内フラックスの決定
10. 2. 2 13C標識化合物を用いた研究によるフラックス推定の評価
10. 2. 3 フラックス解析の細胞培養用培地の設計への応用
11. メタボリックコントロールアナリシス
11. 1 メタボリックコントロールアナリシスの基礎
11. 1. 1 コントロール係数とサンメンションセオレム
11. 1. 2 エラシティシティ係数とコネクティビティセオレム
11. 1. 3 MCAセオレムの一般化
11. 2 フラックスコントロール係数の決定
11. 2. 1 FCC決定の直接法
11. 2. 2 FCCの間接的決定法
11. 2. 3 遷移状態の代謝物濃度の測定値の利用
11. 2. 4 カイネティックモデル
11. 3 直線状の代謝経路のMCA
11. 4 分岐のある経路に対するMCA
11. 5 大きな摂動に関する理論
11. 5. 1 分岐のない経路
11. 5. 2 分岐のある経路
11. 5. 3 基質濃度や外部のエフェクタに対する応答
11. 5. 4 まとめ
12. 代謝ネットワークの構造解析
12. 1 単一の分岐点におけるフラックス分布の制御
12. 2 反応のグルーピング
12. 2. 1 グループフラックスコントロール係数
12. 2. 2 独立な反応の同定
12. 3 ケーススタディ:芳香族アミノ酸の生合成
12. 3. 1 S. cerevisiaeによる芳香族アミノ酸生合成のモデル
12. 3. 2 独立な経路の同定
12. 3. 3 リンク物質の同定とグループフラックスの決定
13. 直交関数系と確率過程
13. 1 グループコントロール係数と個々のコントロール係数の関係
(ボトムアップアプローチ)
13. 2 フラックス測定からのグループコントロール係数の決定
(トップダウンアプローチ)
13. 2. 1 3つの摂動からのgFCCの決定
13. 2. 2 特定の摂動からのgFCCの決定
13. 2. 3 gCCCの決定
13. 2. 4 摂動の可観測性
13. 3 ケーススタディ
13. 3. 1 グループコントロール係数の解析的な決定
(ボトムアップアプローチ)
13. 3. 2 gFCCの実験的な決定の具体例(トップダウンアプローチ)
13. 4 メタボリックコントロールアナリシスの
中間代謝反応グループ解析への応用
13. 4. 1 摂動定数
13. 4. 2 複数の分岐点における重なり合った反応の解析
13. 4. 3 ケーススタディ
13. 5 フラックス増幅の最適化
13. 5. 1 最適化のアルゴリズムの導出
13. 5. 2 ケーススタディ
13. 6 正当性の評価と実験の確からしさ